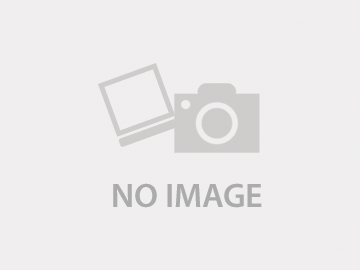高一佐苗が掲げる保守的な政策路線は、自民党の主流派にとっても大きな転換点ですが、何より衝撃を受けたのは公明党とその支持母体である創価学会でした。外交安全保障の強化、憲法改正への本格的な準備、さらには宗教法人の優遇措置見直しといった政策は、創価学会の政治的立場と既得権益に直撃しています。その結果、公明党は緊急の常任役員会を開き、連立政権のあり方を見直す動きに出ました。
公明党の中には、自民党との連立を離脱する可能性を示唆する意見も出ており、背景には創価学会内部で自民党と組むことで組織の力が弱体化するのではないかという不安が広がっています。このような状況の中、自民党内ではむしろ公明党を切ってしまおうという声が上がり始めました。自民党にとって公明党は、政策実現の足かせとなってきたからです。
さらに、憲法20条が規定する「政教分離」という大原則も今回の騒動の背景にあります。創価学会の公明党を通じた政治的影響力が、宗教と政治の癒着構造として問題視されています。これまで選挙の度に創価学会の強力な支援を受けて政権を支えてきた自民党も、今やその支援が消える可能性が現実味を帯びています。
日本の政治が抱える矛盾は、憲法改正、安全保障政策、さらには宗教法人課税といった問題を浮き彫りにし、国民の意識を根底から揺さぶっています。メディアもSNS上での声に後押しされ、戦後政治が作り上げてきた宗教と政治の共存というバランスの崩壊が始まっていることを報じ始めています。これにより、創価学会と公明党の関係についても、本格的な調査や議論が求められるようになりました。
自民党は、創価学会票に頼らずとも安定した政権を維持するため、他の政党との新たな連立構想を模索しています。もし公明党が連立を離脱し、創価学会の政治的影響が減退すれば、憲法改正や宗教法人課税、そして安全保障法制に関する政策が大きく進展する可能性があります。
このように、日本政治の地殻変動は単なる政局の変化にとどまらず、戦後最大の政治的断層を引き起こしつつあります。国家と政治は誰のために存在するのかという本質的な問いに立ち返ることで、日本は初めて信仰ではなく理性によって動く国家へと進化する道を模索しています。